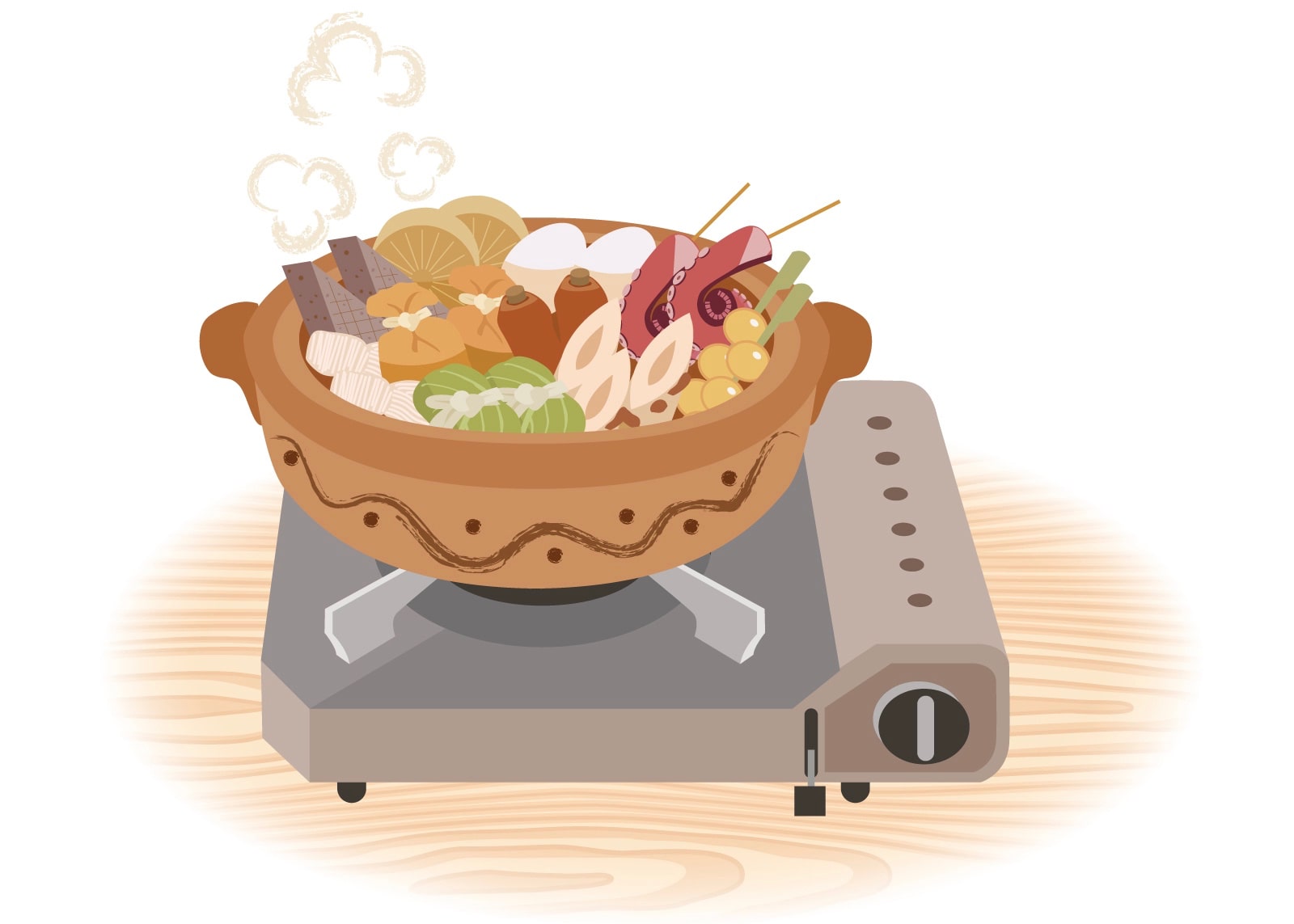家庭料理でもあり、テイクアウトの食品でもあるおでんはとても身近な食べ物ですが、時には高級日本料理店で出されるメニューにもなるという多彩な顔を持っています。
今回は、広く愛されているおでんの由来や歴史、さまざまなバリエーションについてご紹介します。
目次
1.そもそも「おでん」とは?

「おでん」は煮込み料理で、鍋料理に分類されることもあります。味の付いた汁で具材を長時間煮込み、そのまま、またはつけだれと共に食します。
具材やつけだれの種類は地域や家庭によって実にさまざまで、なおかつ日々さまざまなバリエーションが生み出されています。
2.おでんの由来や歴史、発祥について
おでんの名前の由来
室町時代に焼き豆腐に味噌を付けて食べたのが、おでんの始まりとされています。「おでん」は「御田」と書きますが、もともとは室町時代に発生した料理である「田楽」に由来する言葉です。
今では「田楽」というと具材を串に刺して焼く味噌田楽などを想像しますが、具材をゆでた「煮込み田楽」というものもありました。
もう少し詳しく話すと、江戸時代(1603〜1868)に、めし屋が田楽に菜飯とこんにゃくを添えて出すようになり、その後、江戸で田楽を煮るようになって現在のおでんの原型となったのです。
後に焼いたものを「田楽」、煮込んだものを「おでん」と称して区別するようになりました。
そして、江戸時代後期から明治時代初期にかけて、飲食店で提供されるようになり、現在のようなおでんが形成されるようになりました。
その後、練り製品の普及や、1923年(大正12年)の関東大震災で被災した関西の人たちの復興努力により、おでんはより多様な料理となっただけでなく、地域差のある料理となります。
また、田楽から「でん」に短縮され、「お」をつけて、現在の日本全国で売られているおでんになったのです。
おでんの発祥や起源について
江戸時代の初期から中期にかけて、江戸で流行していたのは豆腐やナス、サトイモなどの田楽、関西で流行していたのはこんにゃくの田楽でした。
つまり、煮込みのおでんはまだ一般的ではなかったのです。
煮込みのおでんがポピュラーになるのは江戸の後期、江戸近郊で醤油が生産されるようになってからだと言われています。それが関西に伝わると「関東煮」と呼ばれるようになります。
「関東煮」は関西で改良が加えられ、「おでん」として関東に逆輸入されて広まっていきます。現在のおでんは、この関西で改良が加えられた、薄味のものが主流になっています。
おでんが家庭で普及するまで
関東大震災の折に炊き出しとして使われ、第2次世界大戦後の復興期に広く供されるようになったおでんは、昭和中期になると家庭料理として普及していきます。
そして平成の時代に入り、大きく進化していくのです。
3.意外性抜群!日々進化するおでんの味や具材
おでんの味も進化
おでんと言えば醤油ベースの和風だしのイメージでしたが、平成の時代になると他の鍋料理の影響を受けて豆乳おでんやキムチおでん、カレーおでんなどが登場しました。
洋食のコンテンツを取り入れ、ポルチーニ茸ソースやフォアグラを添えたビストロ風おでん、フルーツを烏龍茶とスパイスで煮込んだスイーツおでんなども登場します。
また、ご当地ブームが反映され、名古屋の八丁味噌味のおでん、串刺しが目を引く静岡おでん、生姜醤油で食べる姫路おでんなども注目されました。
おでんの具材
コンニャク
山芋を使用したゼラチン状のブロック
巾着(きんちゃく)
油揚げの袋。
大根
おでんの定番
牛筋
牛すじ
白滝
こんにゃくでできた半透明の麺
がんもどき
丸い豆腐菓子で、野菜や海藻が入っていることが多い
はんぺん(半篇)
三角形または円形のかまぼこ
竹輪(ちくわ)
筒状のかまぼこ
さつま揚げ(さつま揚げ)
丸い揚げかまぼこで、よくがんもどきと間違われる
おでんの具材には、大根、卵、こんにゃく、昆布など、全国的に用いられているものもありますが、地域性の強いものもあります。例えば、ちくわぶは関東や東北、スジは関西で多く見られます。
さらに近年ではより変化に富んだ具材が利用されています。タコ、鶏肉の手羽など、地域の産品が入れられることもあれば、アスパラやタケノコ、トウモロコシ、ぎんなんなど季節の野菜をおでんの具にする例も増えてきました。
ロールキャベツ、ソーセージなど洋風の素材が具として使われることもあります。
おでんの食べる温度
おでんは体を温める冬の食べ物、という概念は通用しなくなりました。
温かいおでんは1年中食べられていますし、「冷やしおでん」なるものも登場しています。暑い夏でも食欲をそそるおでんです。
おでんの形態
おでんの缶詰が販売されたのも最近のことです。手軽に自動販売機で購入し、缶を開けてすぐに食べられるという簡便さが、若者を中心に受け入れられています。
4.バリエーションが違う!地域別で見るおでんの歴史
沖縄
日本の最南端に位置する沖縄のおでんは、醤油ではなく豚骨ベースの出汁で食べるのが一般的です。
また、沖縄ではおでんの具として豚足が使われることもあります。
静岡
静岡のおでんは、沖縄のおでん同様、醤油ベースの出汁を牛すじと濃口醤油に置き換えたものです。
そのため、ダシは濃い茶色になり、静岡のおでんは独特の風味を持ち、愛されています。
また、イワシやサバなどの魚のすり身を使った「黒はんぺん」も人気で、ダシをより濃くする効果があります。
愛知
愛知県名古屋市では、醤油は出汁のベースではなく、つけ汁として使われます。
八丁味噌で煮込んだ味噌おでんは、あっさりとした甘みがあり、地元産の赤味噌を加えている。名古屋ではおでんそのものを関東煮と呼び、こんにゃくや豆腐を具材として使うことが多いです。
関西
関西では昆布、椎茸、薄口醤油で出汁を取るため、関東に比べて風味が強いです。
関西のおでんは、関東炊きと呼ばれることもあります。
最後に
おでんは、味の付いた汁で具材を煮込むというシンプルな調理法だけに、その応用は無限大です。
今後も工夫が凝らされた変わり種のおでんがどんどん登場してくることでしょう。
自分で好みのアレンジを加えてオリジナルのおでんを作ることもできますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。
 まめ知識生活
まめ知識生活