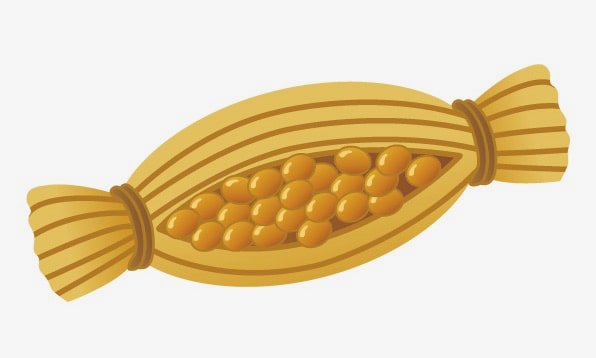納豆はお好きでしょうか。この質問の答えは、大きく二派に分かれるかもしれません。かく言う筆者は、生まれも育ちも関西なので、わが家の食卓に納豆が出た記憶はありません。
でも、大人になって健康に良いということで食べ始めて、今ではそこそこの頻度で食べています。
炊き立てご飯と納豆は本当にベストマッチです。そんな筆者ですが、納豆の由来や歴史、発祥などの豆知識まとめてみました。
目次
1.納豆の由来が知りたい!発祥や起源について

納豆がいつ発明されたのか、その正確な起源は不明であり、納豆がいつごろから食べ始められたかについては諸説あります。
これは、食品の起源に関する物語、特に発酵食品の物語でしばしば見られることで、おそらく世界中の文化で偶然に「発見」されたものです。
ワインやチーズ、ビール、ザワークラウト、コーヒー、チョコレートなど、好みのものを挙げればきりがないほどです。
その中から、これはという有力説いくつかご紹介しましょう。
納豆の始まりは、弥生時代?
ご存知のように、納豆を作るのに複雑な工程は必要ありません。煮た豆と納豆菌との出会いが必須です。納豆菌というのは、空気中や枯れ草、稲ワラなど身近なところにいます。
さて、縄文時代の末ごろ、中国より米の作り方が伝わりました。その後、弥生時代に入って、米や大豆の栽培が日本各地に広がりました。
弥生時代の住居といえば、竪穴式住居ですが、床には稲ワラが敷いてありました。
煮た豆が何かの拍子に稲ワラの上に落ちて、偶然糸をひく納豆になったものが、おいしいということで徐々に食品として食べられるようになったという説です。
納豆は八幡太郎義家(まちまんたろうよしいえ)が起源?
歴史好きならご存知、八幡太郎義家とは、源義家で平安時代後期、前九年の役、後三年の役を戦った武将です。
そのころの戦いには馬が必ず必要でした。その馬の飼料は、煮て乾燥させた大豆でした。
ある戦いの時、敵方がしぶとく、戦いが長引き、飼料が枯渇してしまい、近隣の農民に大豆を差し出すよう命令を出しました。
慌てた農民は、煮た大豆を覚まさず俵に入れて差しだしました。数日後、大豆は匂いを放ち、糸を引いていました。
それを食べてみると、なかなかおいしいので、兵士の食料にしました。その後、農民たちも作って食べるようになりました。
納豆の起源は馬の汗と熱?
納豆が発見されたのは、西暦1080年代の後三年合戦の頃、戦国大名・源義家とその軍勢が北陸征伐に向けて旅をしていた時のことだと言われています。
ある夜、武士たちは田舎の農家に避難し、米と大豆を煮ただけの簡単な夕食をとっていたが、敵が近づいてきたとの知らせを受けた。そこで、馬の餌である稲藁に食料を包んで退却することにしました。
この稲わらは、土中に生息する枯草菌の発酵を促す天然資源であり、藁で包んだ大豆の束は、馬の汗と熱で温められながら、夜通し馬で走りました。
1~2日後に安全な場所にたどり着き、束を開けてみると大豆が発酵しており、美味しく滋養に富んだものであることがわかったとされています。
仏教と結びついた納豆の起源説
7世紀の日本における仏教の勃興と結びついた説があります。この説では、聖徳太子(574-622)が、稲わらに包まれた大豆の小包から納豆を偶然に発見したとされています。
聖徳太子は敬虔な仏教徒で、日本語で書かれた最初の仏教の宗教書を著し、翻訳したと考えられています。納豆はやがて、禅宗の僧侶の精進料理である精進料理において、タンパク質を豊富に含む中核的な存在となりました。
この物語は、納豆が多くの料理、文化、宗教的なアイデアと同様に、中国に由来することを示唆しているかもしれません。 一部の歴史家は、納豆の起源を、中国の周王朝時代、弥生時代(紀元前300年~紀元後300年)に日本に到着した同様の大豆発酵食品に求めることさえあります。
2.納豆の歴史について知っていこう
納豆は、なぜ「納豆」と呼ばれるのでしょうか?「納豆」という言葉が最初に文献に現れたのは、平安時代の「新猿楽記(しんさるがくき)」という書物です。
ここに登場する納豆は、いわゆる糸をひく納豆ではなく、「塩辛納豆(しおからなっとう)」という乾燥させたものでした。
塩辛納豆とは、寺納豆とも呼ばれ、奈良時代に唐に留学した留学生によって伝えられ、寺で作られることが多く、寺の納所=台所で作られたので納豆と呼ばれるようになったと江戸時代の本にはっきりと書かれています。
納豆が広く一般の人々の間で食べられるようになったのは江戸時代になってからです。醤油が安く手に入れられるようになったことが納豆普及に大きな役割を果たしました。
また、納豆というのは、冬場に食べられる季節商品でしたが、江戸時代中期以降は、江戸などの大都会では一年中食べられるようになりました。
そのころは、「ザル納豆」を納豆売りが掛け声とともに売り歩いていました。
3.日本の東西で差がある!?納豆人気はくっきり違う
納豆が好きか嫌いかを表した都道府県別地図があります。くっきり東高西低を示しています。先ほどの由来の八幡太郎義家にまつわる納豆発祥説があるのは東北地方です。
また、「秋田-山形―福島」が納豆銀座であるという説もあります。その地方では、納豆の食べ方のバリエーションが多いのです。
ちなみに、筆者は大人になってから納豆を食べ始めた人なので、卵とたれとからしを入れる以外の食べ方を知りません。
納豆人気が日本の東西で差があるのは、もともと納豆が冬場のものであったこととは無関係ではありません。
しかし、冷蔵技術の進歩により、暑い夏でも食べられるようになったことと、学校給食で納豆が出るようになったことが、納豆人気、納豆消費の地域差を縮めた原因だといわれています。
ちなみに、1965年、最高消費地(福島、水戸、青森)と最低消費地(和歌山、大阪、高知)の地域差が21倍だったのに対して、2004~2006年には2.8倍にも縮まっています。
この縮まり方はすごいですね。
最後に
納豆だからの「豆」知識、いかがでしたでしょうか。ふだん、なにげなく食べている(あるいは、食べていない)納豆についてトリビア、楽しんでいただけたでしょうか。
日本では年間約50万トンの納豆が作られ、消費されています。その中でも、水戸は納豆に適した小粒の大豆を栽培する農家が多く、歴史的に納豆の中心地でもあったので、現在も水戸市は納豆発祥の地であり、日本の納豆文化の中心地です。
健康にいい納豆ですが、嫌いな人も多いので、納豆を食べる人を食べない人が「あんなの食べるなんて!」とけなしたり、納豆を食べる人が食べない人を「あんなおいしいものを食べないなんて!」とけなしたりするのはやめましょう。
 まめ知識生活
まめ知識生活