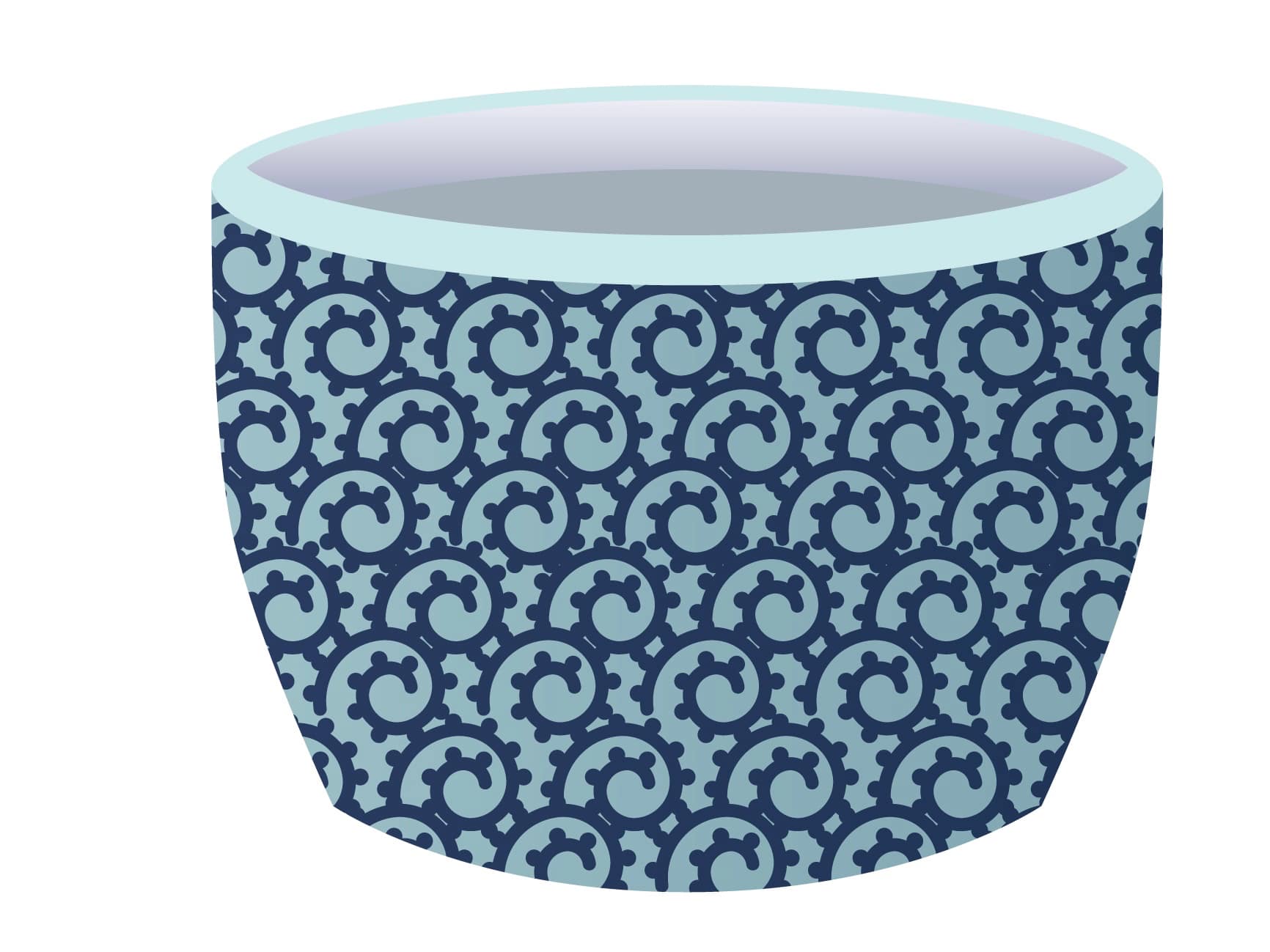今まで骨董品に興味もなかったけれど、街を歩いていると、ステキなアンティークショップを見かけたり、神社の境内で骨董市が開かれていたりして、ちょっと覗いてみたら、なんだかおもしろそう…
高いものは買えないかもしれないけれど、なにかお気に入りの骨董品を買いたいな、と思ったあなたのために、骨董品についての知りたいことをまとめてみました。
1.骨董品とは?

骨董品って、古い時代の、値打ちのあるものっていうイメージでしょうか?はっきりとした定義のようなものはありません。
あえて探すなら、アメリカで1934年に制定された「通商関税法」では、「製造された時点から100年を経過した手工芸品、工芸品、美術品」と定められています。
いずれにせよ、骨董品とは、「古いこと」「希少価値があること」が重要です。特に、絵画とか陶器とかのジャンルは問いません。
骨董品は「アンティーク」とも言いますね。フランス語ですが、ラテン語の「古い」という語から来ています。アンティークに対して、「ジャンク」というのは製造後100年に満たないもの、比較的新しいものというイメージです。
(日本で言う「ジャンク品」とは少しイメージが違います)ヴィンテージとも言いますね。もともとはワインの製造年を表していましたが、それなりの年代を経た、質が良いものという感じです。
古道具という言葉もありますね。こちらは古いものかもしれませんが、あまり値打ちがありそうではありません。
2.骨董品の種類はどんなのがある?
物のジャンルは問わないと書きましたが、美術的な書画(絵や掛け軸など)、陶磁器、装飾品、家具、文具(硯、筆、水滴)、茶道具などさまざまな分野のものがあります。
陶磁器一つをとっても、有名作家の物、古伊万里などから、明治時代の日常使いの印判皿まで値段も大きな開きがあります。
骨董に興味を持ち始めたビギナーさんなら、骨董市を冷やかし半分で見て回るのもいいでしょう。骨董品は、「たくさん見る」ことが大切です。
3.骨董品の値段はどれぐらいで売られているの?
骨董品というのは、ずいぶん前に製造が終わり、どんどん流通しているという商品ではないため、「定価」というものはありません。
ただ、売られていく中で、自然にその商品の価値に見合う相場価格に落ち着いていきます。
骨董品の価格は不変ではなく、年代や希少性、作者、保存状態などとともに、売られる時代、その時の流行などで変動します。
オークションや競りなどでは、何人かで競争になって相場価格をはるかに超えることもあります。
骨董品の楽しみは、掘り出し物を見つけることだとも言われます。
そのものの価値がわからず売られていて、買った方もそれと知らず買ったら、実はすごいものだったというのをたまにニュースで見かけます。しかし、そう出会えるものではありません。
4.骨董品の見分け方は?
テレビの「開運!なんでも鑑定団」は、1994年から続く長寿番組です。
視聴者が持ち込んだ「お宝」を鑑定して、意外なものに高い金額がついたり、高価と思われていたものが偽物だったりすることの意外性が人気を呼んでいます。
普通の人が骨董品を見分けることなんてできるのでしょうか。正直なところ、一般素人が、専門の鑑定士のような鑑定はできないと考えた方がいいと思います。
それほど高度なものでなければ、「落款(らっかん)、刻印、サインを探す」「付属品や共箱(ともばこ)から生産された年代を見る」「素材を確認する」ことはできるかもしれません。
骨董品を見分けるマニュアルのようなものはありません。骨董品は買わなくても、骨董市などでたくさんの作品を見ることで目が養われます。
また、自分が買いたいなと考えている作品や作家について、その作風や傾向について日頃から勉強する必要があります。
「えーっ?!面倒!」って思いましたか?そこが、骨董の醍醐味と言える面白さです。
5.日本の骨董品に関する豆知識
古伊万里(古い伊万里焼)
伊万里焼は、日本の有名な陶磁器であり、17世紀から18世紀にかけて盛んに生産されました。古伊万里は、その初期の伊万里焼で、美しい青と白の絵付けが特徴です。
干支置物
干支置物は、十二支(ね、うし、とら、うさぎ、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い)をモチーフにした日本の陶器や木彫りなどの置物です。日本では、干支を神聖視しており、干支置物は縁起物とされています。
江戸切子
江戸切子は、江戸時代に発祥した日本のガラス工芸品です。緻密な切子模様が施された美しいガラス器が特徴で、日本の伝統的な技術として現在も高い評価を受けています。
紙本蒔絵
紙本蒔絵は、紙に金や銀の粉を蒔いて模様を描く日本独自の工芸品です。平安時代に始まったとされ、装飾品や建築などに使用されました。紙本蒔絵は、日本の美術史において重要な地位を占めています。
歌川広重の浮世絵
歌川広重は、江戸時代の著名な浮世絵師で、「東海道五十三次」や「名所江戸百景」などの作品で知られています。彼の作品は、日本の風景や風俗を美しく描写し、現在も高い人気を持っています。
茶道具
茶道具は、日本茶道で使用される道具の総称です。茶碗、茶筅、茶入れ、蓋置きなどが含まれ、美術品としての価値があるものも多く存在します。
茶道具は、日本文化の粋を感じられる骨董品として愛好家に人気があります。
最後に
いかがでしたかでしょうか。骨董のことについて興味を持ち始めた方が知りたいと思うことをまとめました。
「きちんとした答えが全然ない!」と思われたかもしれません。
骨董品の世界というのは、なにかマニュアルや公式があるわけではないからむずかしいし、でも逆に面白いのかもしれませんよ。
手始めに、なにかひとつお気に入りを思い切って買ってみるのはどうでしょう?
 まめ知識生活
まめ知識生活